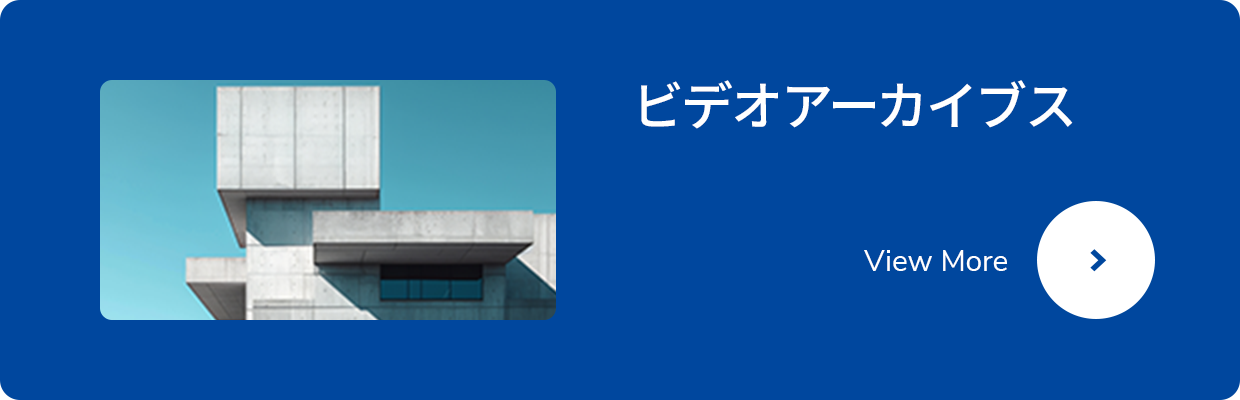第2回 積水ハウスA型と黎明期のプレハブ住宅
 日本の建築市場は明らかに縮小している。そうした中で、設計事務所、ゼネコン、建材メーカー等も海外での事業展開に力を入れてきた。
日本の建築市場は明らかに縮小している。そうした中で、設計事務所、ゼネコン、建材メーカー等も海外での事業展開に力を入れてきた。
日本の現代建築が体現した質には、海外にないレベルのものがいくつもあり、それが海外戦略の武器になると考えるのが自然だが、実際のところそう容易なことではなさそうだ。日本において実現されている高い質の多くが、信頼関係に基づく日本的な商習慣や、日本人の気質に根差した需要の特殊性の上に成り立ってきた一方で、海外にはそうした商習慣や需要特性を同じくする地域が見出し難いからである。「ガラパゴス化」というビジネス用語が想起される。しかしながら、こと新築に関する限り、海外に機会を求めなければ能力を持て余してどうにもならないという事情もある。商習慣や需要特性の違いを乗り越えて、何とか日本的な建築の質を海外でも意味のあるものにしようと挑戦を続ける企業や人は増え続けている。そんな中、日本独自の生産供給体制を築き上げてきた大手プレハブ住宅メーカー各社も本格的な海外事業展開を始めた。
日本のプレハブ住宅はとても特殊で、類似の物や業態を他国で見ることはできない。先ず、日本には年間に1万戸を超える住宅を生産供給する住宅メーカーが複数社存在する。しかも、その中心はそれぞれの個人オーナーの細々とした要望に応えて建設される注文住宅である。こんな状況は日本でしかお目にかかれない。また、それらの住宅メーカーの殆どが、それぞれに自社工場等で生産された部品を組立てるプレハブ住宅を主要製品としている。そしてその主要なものの過半が軽量形鋼を構造躯体に用いた鉄骨造である。日本を木造建築の国だと思って来日する外国人関係者は、国際的に見て特殊なこの事実に目を丸くする。
物や情報が国境を越えて自由に行き交うようになった20世紀後半にあって、何故かくも日本的な産業が形成されたのかは、産業論的にも文化論的にも技術論的にも興味深いところである。そこで、この2年程の間、1960年頃の初期プレハブ住宅の開発に直接関わられた技術者の方々への聞取り調査を続けてきた。 今日も生産供給が続けられているプレハブ住宅の原型にあたるものの内、最も早く開発されたのは積水ハウスA型(1960年発売、当時積水化学工業(株)、写真1)である。幸い、初期から開発にあたった福井佑吉さんと石本徳三郎さんのお二人から直接お話を伺うことができた。
 写真1 積水ハウスA型(1960年、写真:積水ハウス(株))
写真1 積水ハウスA型(1960年、写真:積水ハウス(株))
京都工芸繊維大学建築学科を卒業した福井さんが、戦前の日本窒素の流れをくむ積水化学工業に入社したのは1953年。建築設計者ではなく工業デザイナーを目指しての入社だった。一方の石本さんは1957年に東京大学建築学科を卒業し、建築から離れようという考えで化学メーカーに入った。ところが、そんな二人の入社動機に反して、1959年には突然の社長命令により「オールプラスチックハウスチーム」が発足。石本さんは初めから、福井さんも途中から新たな住宅開発に携わることになり、その後新設された積水ハウス(株)に籍を移し、生涯をプレハブ住宅事業に捧げることになった。
この「オールプラスチックハウスチーム」の経緯については、積水ハウス(株)の30年史及び50年史(同社のホームページ上で公開されている)に詳しいのでここでは割愛するが、同時期のプレハブ住宅の開発の多くに共通する特徴を示す好例と言える。第一に、他産業から住宅市場への新規参入であった点。松下グループが開始したナショナル住宅事業(現パナホーム)や少し遅れて開始された旭化成へーベルハウスやトヨタホーム等の住宅事業も同じ線上にあった。そして第二に、新しい工業材料の販路を成長する住宅市場に求めるものであった点。八幡製鉄等大手鉄鋼メーカーによる軽量形鋼の国産化とそれを用いたプレハブ住宅の開発等もこの線上にあった。
アメリカのモンサント社によるオールプラスチック住宅(1956年)という先行事例に刺激されて始めた開発であったが、石本さんたちはプラスチックを構造体に使うことは早々に断念し、当時出始めだった軽量形鋼を用いることにした。ただ、他の部位には化成品やアルミ等の工業材料を多用し、素人でも組立てられるパネル構法の住宅を目指した。今日のような巨大事業になるとは想像もしていなかった当時は、当然のことながらプランのバリエーションをどう確保するか等の点にも無頓着であった。まだ神戸市内にも建っていた赤や緑の米軍「かまぼこ兵舎」のようなズドンとした空間を、スリーヒンジアーチ形式で実現する構法をイメージしていただけだという(写真2)。当時の石本さんの業務日誌からは、構造計算や材料評価から部屋配置に関する研究のレヴュー、更にはモデュールの検討に関することまで、大学を卒業したての技術者たちが手探りで開発を続けていた瑞々しい姿が浮かび上がる。
 写真2 積水ハウス A型の断面。現在積水ハウス総合住宅研究所内に展示されている。
写真2 積水ハウス A型の断面。現在積水ハウス総合住宅研究所内に展示されている。
何棟かの試作はしていたものの、チームのメンバーがまだ開発途上にあると思っていた1960年春に、上野社長の強い指示があっていきなり発売。積水ハウスA型の誕生である。今日のプレハブ住宅には比ぶべくもないが、この年A型は約100棟程建設された。ただ、A型は屋根の変形という技術的な課題が明確であったため、福井さんや石本さんは発売の直後から次の構法システムの開発を始め、翌年には小屋組トラスを用いた全く新しい構法システムB型を実現した(写真3)。積水ハウスの基本構法システムは今もなおこのB型である。間違いなく世界で最も多くの住宅に採用されたプレハブ構法だと言える。
 写真3 積水ハウスB型の軸組。現在積水ハウス総合住宅研究所内に再建されている。
写真3 積水ハウスB型の軸組。現在積水ハウス総合住宅研究所内に再建されている。
松下1号型(1961年、写真4)ですぐ後に続くナショナル住宅の開発者小林昭夫さんは、奈良にある積水化学の工場敷地内に建っていた試作棟を、隣の田んぼから偵察していたという。
 写真4 ナショナル住宅建材(現パナホーム)の松下1号型(1961年、写真:(株)パナホーム)
写真4 ナショナル住宅建材(現パナホーム)の松下1号型(1961年、写真:(株)パナホーム)
当時既に組立て式の勉強部屋「ミゼットハウス」(1959年、写真5)を商品化していた大和ハウス工業(株)も、この積水ハウスA型に刺激を受けたのであろう、1962年には大和ハウスA型を発売した。いずれもほんの数名の若い技術者のチームが短期間に集中して開発した住宅だったが、1960年代後半には高度経済成長の波に乗り、その後の日本の住宅市場のあり方に大きな影響を及ぼす事業の技術的な種になったのである。
 写真5 大和ハウスのミゼットハウス(1959年、現在大和ハウス研究所内に展示されている)
写真5 大和ハウスのミゼットハウス(1959年、現在大和ハウス研究所内に展示されている)