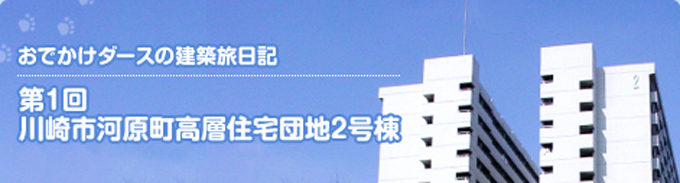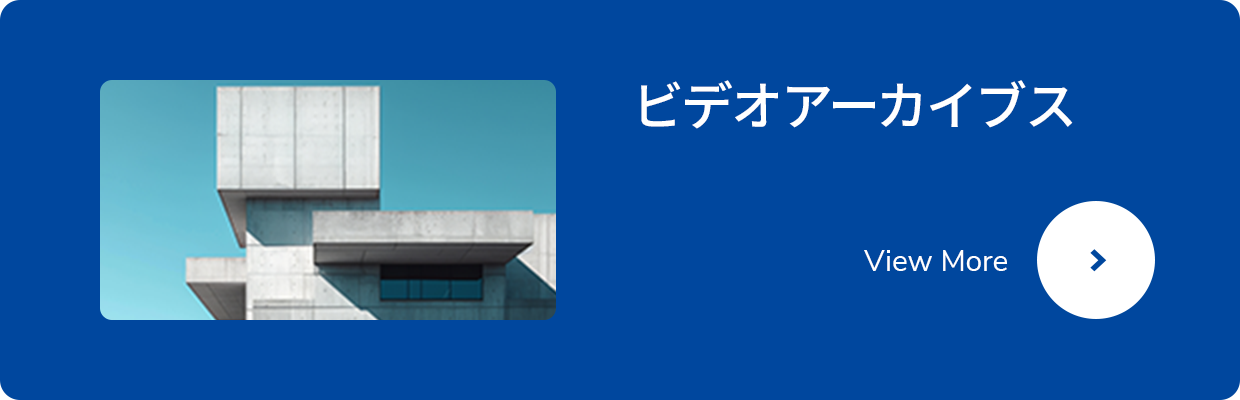第1回 川崎市河原町高層住宅団地2号棟|2006/04/03
おでかけダースの第1回目は、「川崎市河原町高層住宅団地2号棟」を訪ねることにしました。
最初っからマニアックだと言われそうだけど、この集合住宅のことはずっと気になっていて、いつかは訪ねてみたいと思いつつ想いを果たせずにいた、そういう建築でありました。行ってないならやっぱ大したことないんだろって突っ込まないでね。そうじゃないのっ。時間はあるようでそうそうないのだ。
訪ねたのは2006年2月25日土曜日。場所を調べた上で、今度はそれを元に「Google Earth」で空中散歩してみると、ほぼ、当初計画通りに建ち上がっている姿を確認、嬉しくなってさっそく訪れてみた。ちなみに「Google Earth」は最近のお気に入りである。これって便利で楽しいっ!
昼過ぎにJR川崎駅に到着。建築を見に行くときはできるだけ歩いて行くのが周辺環境などが分かってよいので、今回もタクシーはパス。西口近辺は工場跡地の再開発がまだ途中で、いささか回り道をしなくてはならないが、だいたいの方向を定めてウロウロ歩き始める。住宅や商店などの混在したエリアを歩いていると遠方にチラホラ見えてくる。大きい建築はこういうときありがたい。やがて小学校に突き当たったが、校庭越しに並んで見える姿は「ザ・団地」といった感じでなかなか圧巻。その小学校を大きく回り込み、建物のある街区に到着。ここまで駅から約15分くらいだった。
さっそく「2号棟」を目指すが、どうも住棟の番号が事前情報と食い違っている。かつて『新建築』1972年11月号に発表されたときに「2 号棟」と記されていた建物は現在は「7,8,9号棟」となっている。呼称が変わった理由はさておき、ここでは発表されたときの呼称である「2号棟」で通すことにする。
さて、私がなぜこの建築に興味をもったかを述べる前に、まずこの集合住宅の概要と、それがどんなかたちをしているのかを知ってもらおう。この「2号棟」は、これだけで建っているのではなく、延約13.7haという広大な街区に6棟(今の数え方だと15棟?)の巨大住棟群が建ち並ぶ中の1棟である。設計は大谷幸夫(ときどき敬称略になりますが悪しからず)。丹下健三の直弟子に当たる人である。丹下さんの後を継いで東京大学の都市工学科の教授をされた方だから、こうした都市開発規模の計画は本業といってよい。大谷さんの代表作は「国立京都国際会館」(1966年竣工)ということになっているが、都市計画レベルでの建築の提案を本業にされているわけだから、この建築には大いに注目をしたいのです。
話を戻すと、これらの住棟は南北を軸に平行配置されているのがわかる。つまり住戸は東西を向いている。一般的な団地は、日当たりを前提に住戸を南面させた4~5階建ての住棟を東西軸上に平行配置する例が多い。だが、それは南側に壁を立てるような行為でもあるわけで、すべての住戸に均等な日照条件を用意するためには適切な隣棟間隔を設けなければならず、そうすると総住戸数は限られてくる。この「2号棟」のように、住戸の南面配置という条件を外し、建物の東西両面に住戸を配置できれば、廊下を内側(といっても外部ではあるが)で向かい合わせにして、一般的な片廊下型住棟の倍の住戸数をもった一棟の建物をつくれる計算になる。この団地では、そうした大規模な住棟をより間隔をあけて建てるという方向性が選択されている。大規模で高密度、「2号棟」はそういう団地の構成要員として位置づけられている。
廊下を内側で向かい合わせにしたことは、実はこの建築をかたちづくるとても重要な決定であったと思う。廊下に挟まれて生まれた吹抜け空間がデザインの対象になってくるからだ。
14階建ての「2号棟」もその中央部に吹抜けがある。そして、その吹抜けはしっかりデザインされている。下の5層分の住戸が、末広がりに外側に少しずつずれていって、1階部分で幅約30m、長さ約50m、中央部の高さ約30mの巨大な広場を生み出しているのだ(大谷さんはそれを逆Y字型断面とか住棟とか呼んでいる)。平たく言えば、住棟の真ん中に屋根付きグラウンドあるいは体育館が取り込まれているような感じだ。
この広場には、ゴムアスファルト系クッション舗装(当時の雑誌のキャプションにはそう書いてある)が施されていて、バスケットコートやバレーコートのラインが描かれている。だが、雑誌発表時の写真を見ると、コートのラインは描かれていない。そのため、お恥ずかしながら、私はずっとここは土間のような土の床だと思い込んでいた(キャプション、見落としていました。スイマセン)。それは単なる見落としと思い込みなのだが、そう思い込んだ理由は、本当は使い方など示されていないほうがいいな、と、心のどこかで私がそう思っているからだ。だから、この広場は何か目的を持ったことをする場所でなくて、そのときどき好きなことをする場所だろうと勝手に思い込んだ。ここでは、フリマや朝市、消防訓練、運動会に盆踊り、結婚式だってできそうだし、最近ならアートイベントだってフットサル大会だってなんだってアリだろう。とにかくいろいろできたほうが楽しいだろうから、使い方が明示されていないほうがありがたいと思った。バスケットコートとかサッカー専用グラウンドと書かれては、それ以外のことをしたい人は肩身の狭い思いをしなくてはならなくなるでしょう?
私が訪ねたのは土曜日の午後だったが、時折、一輪車の練習や、楽しそうにでもやや遠慮がちにサッカーボールを蹴って遊ぶ子供たちが見られた。
この空間はとても新鮮な体験だった。グラウンドのようでグラウンドでなく、体育館のようで体育館ではなく、ガレリアのようでガレリアでもない、これまで見たことのない質の空間がそこに広がっていた。広場のことだけ先に書いてしまったけれど、その質は、この広場を住居群が覆っている構成に大きく起因すると思う。骨太な架構や吹抜けから射し込んでくる陽光も空間の演出には役立っているが、これを生み出しているのはこの空間の組合せ形式にあると思うのだ。 それを最近の建築論っぽくいうと、小さな単位(つまり住戸)の組合せ方に大きな可能性を見せてくれている建築である、といえよう。昨今の集合住宅のつくられ方は、集合させる単位のバリエーションのほうへ意識がいっていて、画期的なコモンスペース創出への眼差しはあまり見られない(その必要性を求められなくなっていることもあるが)。それに対し、ほぼ同一の住戸単位の集合のさせ方でこのような空間をつくり出せることを示した点が、この建築の大きな魅力だと思う。
小さな単位空間(ハコといってもよい)を、どのように配置するか(どのように積むか)を考えることは、建築を設計するひとつの大きな原理のようなものだから、逆手にとれば、さまざまな建築をハコの積み重ねに置き換えて分析することもできる。そう考えると、大きなアトリウムに客室が面するホテル建築などが「2号棟」に近い形式だといえるが、この構成を集合住宅というビルディングタイプでやった例はほとんどない。少なくともこの規模の広場を内包した集合住宅は日本にはここにしかない。
このような空間構成を持ったことで「2号棟」は、この広場で発生するいろいろな人たちのさまざまなアクティビティ(ベタだけど、遊び回っている子供たちの声や気配などというのはその一例だと思う)を家にいながら感じ取れる建築たり得た。このような人と人との関係は集合住宅では滅多に起こり得ないすごいことだと思う。それが、構成単位である住戸を積み上げて内側に広場をつくりだすこと、という設計手法によって生み出されている。その辺が私の感心したところである。 やっぱ、見に行ってよかった!
この建築のアイディアのルーツを考えていたら、大谷さんの師匠である丹下さんが、かつてMITでスタジオを持ったときに、学生たちとつくり上げた「25,000人のコミュニティ計画案」(1960年)の断面が、規模は違うけれど(内部道路を車が走っちゃうくらいなので……)同様に住戸単位を傾斜配置して内側にコモンスペースを包み込んでいたことを思い出した。このときのプロジェクトは丹下さんにとっては「東京計画1960」につながるものであったというから、そばにいた大谷さんがこの計画案を知らないはずはなかろう。そう考えると、丹下研で構想された都市居住のひとつのかたちが、遺伝子として大谷さんに組み込まれ、10年をかけてじわじわと建築的実現をなしていったのだろうと想像できる。これをただの真似といっては身も蓋もない。アイディアの発生から熟成、実現までは、それなりに時間のかかるものなのだ。
では、それだけ大発明の空間だと褒めちぎっておきながら、なぜこの方法は広まらなかったのか? いくつか理由は想像は出来るが、それはこの先の宿題とする。今回は高度成長時代の後期に日本において構想された都市居住への提案的な空間を確認したところで終わりにしたい。 初回ということもあって、どうも、肩に力が入ってしまったけれど、今後はもっとラフな雰囲気で書いていけたらと思っています。それではまた。(は)
webadvisor swc mypisd.net Mayfatnaxiwoods . Vewessekubad . Comnoketwellpet Seofuncnesscydab Ahphylfaresgu .