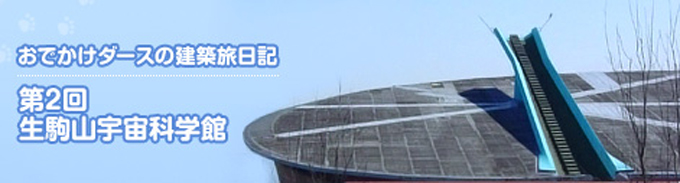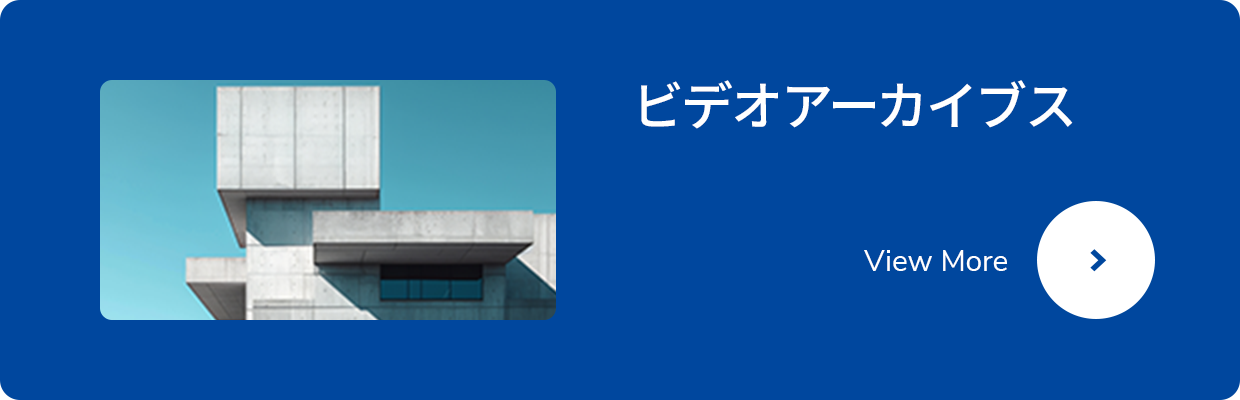第2回 生駒山宇宙科学館|2006/12/18
おでかけダースは東京在住なので、基本的に東京近辺へのおでかけが多い。しかし、出来れば出張ダースもしたい、と思っていたら、たまたま機会があったので第2回目は関西編にします。
しかしその記念すべき関西編第一発目が……残念ながら廃墟紹介になってしまいました。
といってもわざわざ廃墟を訪ねたわけではない。以前から気になっていたのだけれど、今回見に行ったらすでに閉鎖されていただけのことである。たいへん悔しいことだが、早く見に行かなかった自分が悪いのでしかたがない。
しかし一方で、このアーカイブの存在意義は、実物が消滅したり見るに堪えない状況になったりした建築の資料保存にもあるわけだから、廃墟系を取り上げる価値は十分にあると思う。
その第一弾は「生駒山宇宙科学館」。
廃墟とはいっても、今回は運良く外観だけは見ることができた。
この建物は、1960年代末に、奈良県と大阪府の境目、生駒山山頂部の近鉄が経営する遊園地の一角に、今でいうテーマパークの目玉施設のようなものとして建てられた。『新建築』1970年3月号に掲載されており、設計は早稲田大学教授の吉阪隆正さんである。
1960年代末というのは、1969年にアポロ11号が人類初の月着陸を果たし、1970年開催の大阪万博アメリカ館の人気は月の石と月着陸船だった、そんな時代である。当時、「宇宙」と「科学」は子供たちの夢だった。
子供たちのあこがれを背負って建ったこの建物は、なぜか実にヘンなかたちをしている。卵形の平面にロケット発射台のような巨大な大樋が乗っかっている造形は、あれこれ突っ込みようのない恣意的なかたちである。
この建物は、奈良県側から見ると、生駒山の稜線付近にへばりつくように建っていて、その姿を生駒の街から見ることができる。ちょうど、「○○岩」などと呼称される特異な景観のような姿であり、機会があったら見に行ってみようと思っていたのだった。
で、行ってみたのは、2006年3月25日。
近鉄奈良線の生駒駅から南西に延びるケーブルカーに乗り、終点の生駒山頂駅で降りて訪ねるのが一般的だが、今回は事情により、車で信貴生駒スカイラインを通り、大阪側から遊園地の中を抜けてアプローチした。
建物は、遊園地のもっとも低いところに、東を向いて建っており、遊園地側から近づくと、卵形の屋根面にコンクリート製の大樋が乗っかった光景が、かなり低 い位置に見えてくる。屋根面が片流れのため、その姿は、建築と言うよりも楕円形の広場というか、ステージというか、円盤状の地形として見えてくる。
遊具の間を下ってそばに寄ると、大きな屋根面は徐々に隠れ、代わりに外側に傾斜した逆円錐状の壁面が存在感をもって立ち上がってくる。その壁面を東側に回 り込むと、生駒市側に向かって、巨大なハーモニカのようなかたちの四角いヴォリュームが、建物に貼りついているのが見えてくる。そばに寄ると、壁の高さ、 壁面の傾斜、四角いヴォリュームのサイズ、その持ち出し寸法などから、この建物のスケールとヴォリュームの大きさが際だってくる。
この建物の外壁はコンクリートだが、通常の建築の外観に見られるような、物差し代わりになるモデュールや目地、一般的な建築部品がほとんどついていないた めに、建築が構成要素に分割されて見えてこない。そのせいか、この建物は、建築というよりも土木構築物のように見える。ダムや貯水槽のような感じであり、 休憩室だったハーモニカ状のヴォリュームは、あたかもダムに添えられた監視室のようだ。こうした建築的構成要素の不可視性は、一体成型が可能なコンクリー ト構造の特徴でもあるのだが、この建築は、その不可視性によって実際以上のスケール感を獲得している。そして同時に非建築的な形態の存在感も存分に発揮し ている。
この建物を、土木的でなく建築的に見せている部分があるとすると、それは、屋根の架け方だろう。図面を見ると屋根は鉄骨造であり、トラス梁がロケット発射 台のような大樋を支える大柱から外周部へ向けて放射状に架けられている。この屋根架構は外壁にべったりと接することはなく、少し浮かせて載せられている。 構造形式が違うとはいえ、土木ではこんなことをわざわざ表現したりしないから、ここには建築の作法が生きている。しかしその軒裏は、場所によっては軒先が 上がっているところもあり、タブーも平気でやっている。
この曖昧な曲面壁、屋根が壁面からわずかに浮いているところを指して、吉阪さんの師匠であるル・コルビュジエのロンシャンの教会堂との類似を語ることもできるかもしれないが、それを指摘したところで話は先へ進まないので、観察と分析を進める。
この外壁面には、ところどころに、四角錐状の開口部がはめ込まれており、そこだけ妙にディテールが精緻である。本体のノンディテールな荒々しさに比べると実にアンバランスである。
だが、いちばん不可思議なものは、なんといっても東の空へ向けて架けられたロケット発射台のような大樋だ。屋根や壁の一部を削り取り、大地から空へと向け て架けられたこの大樋は、ほとんどの部分が樋としての機能を果たさない。その代わりに、というのも何だが、樋の底に一直線に伸びた階段がつけられている。 天国への階段のようでもあるが、18世紀にインドでつくられた天文台「ジャンタル・マンタル」によく似ているので、意識は天国と言うより宇宙への意識だろ う。宗教ではなく科学だ。
宇宙の秩序を建築に持ち込む、という意志がこの部分に込められていると感じた。それも、イメージやオマージュからではない。設計の手がかりを、安易に周囲の地形や用途に求めない、という意志のように理解した。
内部空間については、見ていないので雑誌や作品集からの推測でしか語ることができないが、卵形平面の片側が2層に、もう片側が天井まで吹抜けの大空間に なっていて、仕切りの壁はないので、基本的には一室空間といってよかろう。その中に球形のプラネタリウムと大柱が立つ。吹抜け部分にはアメリカ製の大型ロ ケットが屹立している。外側に傾斜した内壁面には、散策路のような階段が直に取り付けてあって、それによって、ロケットをさまざまな高さや角度から見るこ とができるようになっている。この階段はまるで山岳都市の石段のようでもあり、そこを登る人にとっては、外側からは不調和に見えた四角錐の開口部も、ちょ うどよいスケールのオブジェに見えていたのではないだろうか。なのでこの建物の壁は、内側では「建築の壁面」ではなく「大地の傾斜」のようなものと位置づ けられていたのではないだろうか。
「大学セミナーハウス本館」と同じく大地に深々と突き刺さったような逆円錐型ヴォリューム、閉鎖的な外観、宇宙へと向けられた大樋に見られる周辺地形との 関連性の薄さ、アンバランスに見えたり非建築的に見えたりするスケールのコントロールのしかたなどから見てゆくと、吉阪さんは、建築を構成するかたち、そ のかたちの選択の前提となるパラメータの設定も、同時代の一般的な建築に使用されている既存のボキャブラリーの外側から持ち込みたかったのではないかと思 えてくる。
一方でこの建築からは、建築というものは自然と強烈に対峙する明確な人工物であるという意識、自然に対し安易に手を差し出したり、融和しよう、擦り寄ろう としてはいけないという意志を感じる。にもかかわらず、遠望すれば「○○岩」のようでもあり、上から見下ろせば楕円の台地のようでもあり、環境との連続性 を考えていないわけではない。むしろ独自の親和力によって一体の景観になり得ている。
離れて眺めてみてなじんで見えてくるかたちのありよう。
建築のかたちと自然環境の間に生じる関係性について、吉阪さんはそのように考えていたのではないか。だとすると、ここでのかたちの決定のしかたは、建築の 環境への位置づけ方としてはかなり斬新なものだったのかもしれない。気軽にヘンなかたちなどとは言ってはいけなかった。この建築においては、訪れる人間の 側に、建築との適切な意識の距離の設定が求められているのだった。それを非人間的だなどと怒ってもいけない。安易なヒューマンスケール至上主義は、ここで は注意深く避けられているだけなのだ。つまり、建築と自然との関係、人間と自然との関係、人間と建築との関係がそれぞれ等価に扱われているということで、 どれかひとつの関係だけを特別扱いしていないということだ。これは簡単なようで難しいことだ。
吉阪さんにとってこの場所に建築をつくることの意味は、自然と建築と人間の間に生じる関係性を、先述のように再定義して見せることだったように思える。そ のためには、この建築には既存のデザインボキャブラリーからは援用不可能な新しいかたちが必要だった。三つ巴状態を形態化したいという意志が、この建築か らは感じられる。
建築は、物理的にはそれが位置付く場所との関係で成立するが、その時に何をそのかたちの手がかりにしたかは、その意匠の中から見て取れてしまう。そこには建築家の裸の思考が露呈してくる。知識も教養も思想もすべて丸裸だ。だから建築の設計には深慮が必要だ。
私には吉阪さんは、建築と自然と人間は鼎立すべきという思想をもってこの建築の設計にあたり、同時にそのような意志に基づいて造形されるべきだと考えたように思えてならない。やはり吉阪さんはなかなか奥深い。(は)
Seofuncnesscydab . Ahphylfaresgu .