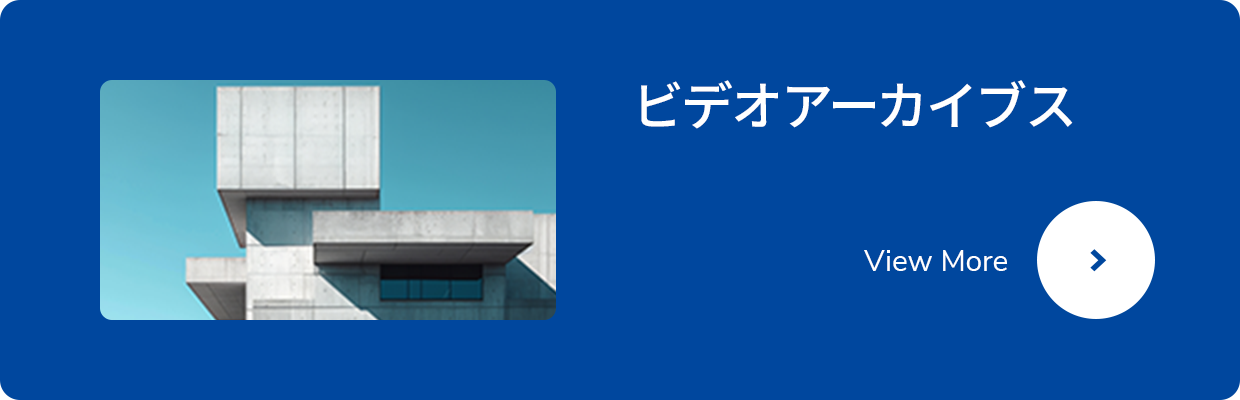第3回 PL学園幼稚園|2007/11/22
第2回で、廃墟系を取り上げた。そのときはまだ外観は見ることが出来たが、今度のは門前払いだった。
おでかけ先は、相田武文の代表作と言ってよい「PL学園幼稚園」。
訪ねたのは、2006年3月24日。大阪府富田林市に位置するPL教団本部の敷地内にあるので、教団本部を訪ね、見学を申し出たところ、数年前に新しい幼稚園が出来て、現在は使っていないために、見学はお断りしているとのことで、めでたく門前払いとなった。
見に行って書くのを原則としたが、行くには行ったが見ることが出来なかった建築については、書くべきかどうか迷うところである。でも、書いておこうと思った理由は、今後も、「見に行ったけれど、見ることが出来なかった、あるいは建物がなかった」という可能性が増えるだろうから、そのことも記しておこうと思ったことが第一。そしてもうひとつは、この建築が『新建築』の1974年1月号に掲載されたときに同時に掲載された相田さんの文章に興味を持ったから、である。
相田さんは、4つの立面を芝生の法面で囲んだこの建築の構成論理が、それまでの自分の作品「無為の家」「涅槃の家」「さいころの主題による家」の延長上にあると述べている。
芝生の法面で建物の外観を消し去ったかのようなこの建築と、まるで建物に顔でも付けたかのような、強い恣意的意匠を持つ3つの住宅が同じ考え方だというのである。
そんなことがあるのか? と思った。こういう疑問をそのままにはしておけないので、まずはその文章を全部読んでみた。すると、相田さんがそこで述べていることが、その後の、相田さんとはほとんど無関係に思える建築思潮に、見えない線でつながっているように、唐突だが、感じられてしまったのだ。なので、今回は相田さんの組み立てた創作の論理を追いながら、少し脱線しつつあれこれ考えてみたい。これも、言ってみれば70年代の建築をめぐる旅の一種だと私は思う。
まずはじめに建物の概要を述べておくと、敷地は、前述の通り、大阪府富田林市の西の丘陵地に広がるパーフェクトリバティ(PL)教団大本庁内で、竣工は1973年。機能は幼稚園である。敷地は東西に長く、西側に屋外遊戯施設、東側に園舎が建つ。園舎は平屋で約40mの正方形平面、立面は4面とも土を盛り芝を張った法面である。法面の勾配は約27度で、園児を遊ばせ、安全性を確認した上で決定したと言う。各法面の中央部に設けられた4つの入口から中庭に入り、そこから諸室へアクセスするので廊下のない平面である。平面はひとつながりではなく、その入口によって4つに分割されている。管理ブロックとふたつの教室ブロック、教室と遊戯室を一緒にしたブロックの4つである。諸室は、天井の高さが全体構成から決まってしまうため、部屋に入隅出隅を設けたり、床面にレベル差を設けて空間の変化と性格付けをしている。また、片側からしか空気の出し入れが出来ないため、部屋奥のガラリから天井裏に空気を取り込み、全面エアチャンバーとした天井裏を通して中庭側へ換気扇で排気している。暖房は地域暖房から熱源供給を受け、床下にファンコイルユニットを設置して床吹出しとしている。椅子、机などの家具も相田さんがデザインしている。
建築概要は、ざっとこんな感じである。
続いて、相田さんの論考をみていきたい。
相田さんは、この幼稚園を発表した号の『新建築』に、「建築が消えるとき」と題した論考を寄せている。芝生の法面によって立面が消えているので、そのタイトルは「見たまま」なのだが、話はそれでは終わらない。なぜなら、相田さんはその冒頭で、前述したように「この幼稚園も形態論的に見れば、これまで発表してきた「無為の家」「涅槃の家」(『新建築』1972年8月号)「サイコロの主題による家」(『都市住宅』第5集)などと一連のものである。この3作品とも建築における用途と形象の問題についてテーマを設定したものである」と書いているからだ。
相田さんは、その文中で、自分はこれまで「内部の用途と立面の関係」をテーマにしてきたこと、それに則して言えば「幼稚園という校舎の持つ用途としての表情は現さない」こと、それは近代合理主義建築が建築内部の用途をそのまま立面に現したことや、施設に付着した慣習的・形式的・形態的イメージが「何々らしさ」として建物の外観を決めてしまうようなやり方を否定してのことであること、自分がこれまでやってきた手法は「結果的にきわだつのであって、きわだたせることを目的としたものではない」こと、それは「建築を消す一過程」であったこと、などを語っている。
「内部の用途と立面の関係」をめぐる問題は、昨今の「ナカミとカタチ」の関係についての議論と同根だと言えよう。だからこの問題は、ロバート・ヴェンチューリの名著『建築の複合と対立』(原著は1966年刊、最初の日本語翻訳本は1969年に美術出版社から出版された)において言及されたデコレイテッド・シェッドとダックの対比問題に接続する論点であり、この著作の近年の再評価も考えれば、今日の建築思潮につながるものであると言える。
ただ、そういったところで、相田さんの説明だけでは、どうしてファサードがサイコロになるのかがわからない。そこで、理解の手引きとして同じ号に掲載されている長谷川堯さんの論考を参照した。長谷川さんは、1970年代の建築思潮に大きな影響を与えた建築史家・建築評論家である。
長谷川さんは、相田さんの建築には「建築を通しての〈対他存在〉の思惟」の意識があると言う。いきなりそう言われてもなんのことだかよくわからないが、読み進めてゆくとそれは徐々に解題される。
まず〈対他存在〉とはサルトルが提唱した対概念であり、「他者にとっての私の意識」であると言う(ちなみにもうひとつは〈対自存在〉=「自己についての意識」だそうである)。
この〈対他存在〉を相田さんの建築に即して言えば、それは「私が他者によって所有される」意識、あるいは「私を他者に所有してもらおうと企てること」、あるいは「私の主観性から逃れるために、他人の主観性のうちに自己を失おうと企てること」なのだと言う。
これでようやくわかってきた。
つまり、相田さんの建築におけるファサードは、内部の用途とか、作家の主観性によらないデザインをつくり出す論理としてあり、そこにおいて、建築に仮面をかぶせる(つまり「私の顔」を否定する)という方法を考え出したということだった。
作家自身の主観性から離れるということ。これを「非作家性」と呼ぶなら、相田さんの考えたことは、『新建築住宅特集』1998年3月号に掲載されたみかんぐみによる論考「非作家性の時代に」にもつながることになる。
しかし、約15年の年月を隔てた両者の建築は、とても同じ意識をもってデザインされたものとは思えない。しかも、意匠上の主観的表現を消すために、他者の顔なり姿なりを持ってきて外側に貼り付けたところで、主観性の消去が達成されると言えるのか、とも思う。仮に主観性を消去できたとしても、そこには恣意性の強い別の異形が出現するだけで、建築の表現から、主観性に基づく操作が生み出す恣意性の強い意匠を外したことにはならないし、そもそも意匠に「テーマを設定」すること自体が、主観性の主張ではないか?
やはり、主観性と作家性は違うものなのか? それはやはり現時点では区別して語るべきだろう。作家の主観性を消すか消さないか、といった作家意識ごと葬り去ろうというのが、前述のみかんぐみの論考の主張なのだから。
しかし、相田さんの主観性の消去手法にあれこれと疑問を呈してもなお、その後の非作家性に通じる意識が、相田さんの文章中に見え隠れしているように感じてしまうのはなぜだろう。
相田さんは前述の論考において「本来は風化して都市の中に、田園に消えてゆくことを願っている。それは建築を自然の中に帰してやるということなのだ」とも述べている。これは、この建築が民家のように風景に溶け込み埋没してゆくことを肯定している発言である。そしてこの意識は、その後の非作家性の考え方に通じるものだと言ってよいのではないか。そうした意識を、主観性の消去という論法に基づく手法よって出現させたのが、この幼稚園だったのではないか? と私は感じている。その後の非作家性の論理に比べれば、主観性の尻尾を切りきれていない論理と言わざるを得ないが、その甘さは単純な両者の思考の深浅だけではない。
世代の違い、時代の違いの何かが作用している。そう考えると、私はこの両者の「論理」の立て方、「結果」の出し方の違いに興味が湧いてきたのだった。両者の根底には、建築のありように対する共通の想いがあるのではないか? あるとしたらそれは何だろう? 事例を漁りながら、歴史的背景を洞察しながら、あれこれ考えてみたいと思っている。