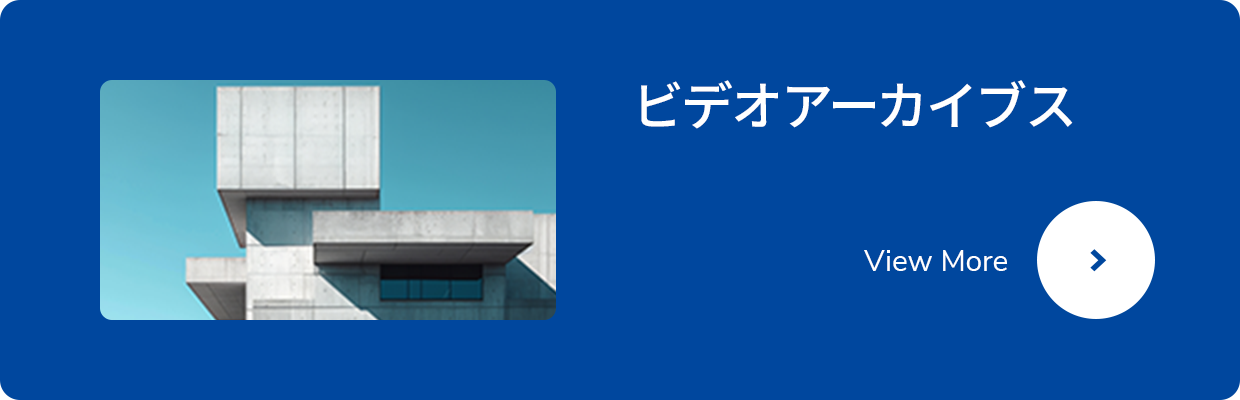第4回 50年前の公団住宅が空き家になり、そしてこうなった -多摩平団地とたまむすび テラス-
 前回はUR都市機構の「集合住宅歴史館」について触れた。また、「個人的には、2階建がそっくり復元された多摩平団地のテラスハウスが好きだ」とも述べた。今回はその多摩平団地で最近起こっている興味深い動きについてである。
前回はUR都市機構の「集合住宅歴史館」について触れた。また、「個人的には、2階建がそっくり復元された多摩平団地のテラスハウスが好きだ」とも述べた。今回はその多摩平団地で最近起こっている興味深い動きについてである。
2009年、UR都市機構は、昭和30年代に建設された公団住宅を取壊すことなく再生させる効果的な方法を見出すため、ルネッサンス計画2「住棟ルネッサンス事業」を開始した。URが公開した資料によると、同年8月には、その第1ステージとして、多摩平の森(建替前団地名:多摩平団地、東京都日野市)、ひばりが丘団地(東京都東久留米市・西東京市)、東綾瀬団地(東京都足立区)の3団地を対象として、広く民間事業者から住棟の改修・活用に関する事業アイデアを募集し、実現可能性のある事業提案者を団地ごとに選定した。そして、2010年4月には、第2ステージとして、多摩平の森(かつての多摩平団地)において、第1ステージで選定された事業提案者(6者)に対し、3画地計5棟(約1.3ha)の住棟を対象として、実際に住棟を改修して住棟の躯体等を賃借する事業企画提案の受付を行い、3つの事業者を決定・公表した。
私自身も第2ステージに事業企画審査会委員として参加したので、既に空き家になっていた5棟から成る対象敷地には何度か通い、50年前に建てられた典型的な中層の初期公団住宅が、民間事業者の手によって一体どのように甦るのか、興味津々だった。そして2011年秋、ついに一新したその姿が「まち開き」という形で公にされた。
UR都市機構の前身の一つは1955年に設立された日本住宅公団である。鉄筋コンクリートの集合住宅自体は同潤会アパートに代表されるように戦前からあったし、戦後も公営住宅の分野では昭和20年代から建設されていた。しかし、鉄筋コンクリート造集合住宅の大量供給のための計画技術、生産技術を確立したという点で、日本住宅公団は歴史上特別な位置にあると言って良い。住戸・住棟の標準設計、団地計画、ティルトアップ工法から始まるプレキャストコンクリート大型パネル構法、ステンレス流し台に代表される住宅部品の数々等、日本住宅公団は1950年代後半から1970年代前半にかけて明らかに日本の集合住宅分野を先導する存在だった。多摩平団地(1958年管理開始、建替え前戸数2792戸)はそうした日本住宅公団の最も瑞々しい時期に建設された大型団地だった。しかし、テラスハウスが集合住宅歴史館に移築・展示されていることからもわかるように、当時の公団住宅はその多くが姿を消し、今や取壊されずに残った住棟は、今回「住棟ルネサンス事業」の対象となった5棟だけである。
新しい事業者による工事が始まる前に、この5棟とその周辺敷地の再生をテーマに大学での設計課題を出したことがある。この課題を選んだ学生たちと共に何度か現地を訪ねた。鉄筋コンクリート壁式構造による4階建ての住棟は階段室型で、畳敷きの3室を持つ3Kタイプ(専有床面積42.3㎡)の標準設計による住戸計144戸から成っていた。(図1〜2)
 図1 元の住棟の平面図(資料:UR都市機構)
図1 元の住棟の平面図(資料:UR都市機構)
 図2 元の住棟の立面図(資料:UR都市機構)
図2 元の住棟の立面図(資料:UR都市機構)
耐震改修を必要としないその躯体はまだまだしっかりしているようだったし、南面と北面で使い分けられたスチールサッシと木製建具も50年前のものがそのまま使われていた。学生たちに言わせれば「少しきれいにすればまだまだ住めるじゃないですか」という体だったが、何より学生たちの気に入ったのは住宅地としての伸びやかさだった。住棟の高さが4階建てと低い上に、隣棟間隔は広く、ところどころにちょっとした広場も配置され、木々が大きく育っているのだから、今日のせせこましく配置されたマンションや小規模戸建て住宅でできた緑の少ない町を見慣れた目には、50年前のこの豊かさは予想外の発見であったに違いない。私にも学生たちにも、この伸びやかさ自体がここにしかないものであり、将来に向けて引継ぐべき住環境の質であるとの思いが募った。(写真1~3)
 写真1 再生工事開始前の状態(住棟と南側の屋外空間:当時の学生の撮影による)
写真1 再生工事開始前の状態(住棟と南側の屋外空間:当時の学生の撮影による)
 写真2 再生工事開始前の状態(住棟に囲まれた広場:当時の学生の撮影による)
写真2 再生工事開始前の状態(住棟に囲まれた広場:当時の学生の撮影による)
 写真3 再生工事開始前の状態(北側の和室と木製建具:当時の学生の撮影による)
写真3 再生工事開始前の状態(北側の和室と木製建具:当時の学生の撮影による)
50年前の建物を建替えることなく使い続けることは、この環境全体の特長を引継ぐ最も確かな方法である。そのことは今回の事業においてUR都市機構も強く意識していたであろうし、提案事業者はそこにこそ民間市場での訴求ポイントを見出していた。
南側の2棟をシェアハウスに改造した「りえんと多摩平」では、南側にオープンデッキとそれに繋がる緑道を設け、隣棟間は屋外でのパーティも楽しめるコミュニティスペースに仕立て直している。真ん中の1棟を菜園付き住宅に改造した「AURA243多摩平の森」では、階段室側に住民が借りられる小屋付き菜園と共同の作業スペースを設け、北側2棟を高齢者向け住宅に改造した「ゆいま~る多摩平の森」では、その菜園の方に向けて少し張り出す形で、外部に対してもオープンな食堂を設けた。事業者は異なるが、URの意向もあり、この5棟とその外部空間はゆるやかに一体の住環境を形作り、周辺のまちに対しても開かれたものになっている。その全体にも「たまむすびテラス」という統一名が付けられている。(写真4~6)
 写真4 りえんと多摩平(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
写真4 りえんと多摩平(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
 写真5 AURA243多摩平の森(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
写真5 AURA243多摩平の森(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
 写真6 ゆいま~る多摩平の森(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
写真6 ゆいま~る多摩平の森(撮影:芝浦工業大学南一誠研究室)
たまむすびテラスの詳細は、URのサイト「ルネッサンス計画2(多摩平の森 ルネッサンス事業)」を初め、既に様々な媒体で紹介されているので割愛するが、異なる住棟の住民同士の交流はもちろん周辺住民との交流も始まり、期待通り、なかなか他所で見ることのできないのびやかな環境の中でいきいきとした生活が展開され始めたようだ。URと事業者の間に交わされた定期借家権の設定期間はそれぞれ15年或いは20年なので、少なくとも2020年代半ばまでは昭和中期の空間的なのびやかさが継承されるものと期待される。
昔の姿に忠実な保存も良いが、古びた環境に独自の良さを見出し、現代的なアクティビティを盛り込む形の再生事業も挑戦的な課題だ。その先駆的な取組みであるたまむすびテラスの持続的な活動に大いに期待したいと思う。